埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
土日祝・時間外も柔軟に対応します
埼玉 相続登記
<簡単まとめ:このページから分かること>
ケースに応じて「相続登記の手順・必要書類」について、ケースごとに御案内しており、相続登記手続に関する疑問点は、ほぼ解決できる内容になっております。
どの位の費用がかかるのか気になる方は、事前に御見積もりいたします。(遠方の不動産に関する相続登記も対応可能です。)
また、「相続登記手続について何から始めたらいいのか分からない」・・といった御相談も承っております。
(よく御相談いただく内容)
①相続人の中で音信不通(行方不明)の者がいる
②相続人の中で関係性の悪い者がいて話し合いが困難である
③相続人の中で海外在住の者がいる
④相続人の中で未成年者がいる
⑤相続人の中で認知症の者がいる
⑥相続不動産を全て把握していない・・など

相続登記に関する改正等ポイント
- 1相続登記の申請が義務化されました。(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されました。義務化されると、相続登記を放置された場合、10万円以下の過料が課される可能性がございます。(ただし、相続関係者が多すぎてなかなか遺産分割協議がまとまらない等正当な理由がある場合は除きます。)
<原則>相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
<例外>遺産分割が成立した場合、遺産分割成立時から3年以内に相続登記をする必要がございます。
尚、令和6年4月1日以前に発生した相続についても(1)令和6年4月1日、もしくは(2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
今後は、なるべく早めに相続登記をおこなうことをお勧めします。
<よく御相談いただく相続登記の内容例>
①数年前に親が亡くなっているが、実家の相続登記を済ませていない。
②何代も前から相続登記を行っていない。
③相続登記を済ませていたと思っていたら、私道部分の相続登記が完了していなかった。
④遠方の投資物件の相続登記を済ませていない。
- 2令和8年4月1日から「住所変更登記」・「氏名変更登記」が義務化されます。
令和8年4月1日から所有者の住所や氏名が変更となった場合、変更となった日から2年以内に変更登記をしなければなりません。(義務化)
尚、正当な理由なくこの義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がございます。
また、義務化される令和8年4月1日より前に住所や氏名変更があった場合は、令和10年3月末までに変更登記をする必要がございます。
- 3相続登記手続きがうまく進められない場合、代わりに「相続人申告登記」が利用できるようになりました。(令和6年4月1日施行)
相続人間で話し合いがまとまらない場合や相続人の一部が行方不明で遺産分割協議ができない場合などの事情がある場合、上記の3年以内に相続登記ができないので、より簡易に相続登記の申請義務を履行できるように「相続人申告登記」という制度を利用することができるようになります。
この「相続人申告登記」は、登記簿上の名義人に相続が発生したことと、申告したものが相続人であることを登記官に申し出る制度です。この申し出をすることで、職権で申出をした相続人の氏名、住所等を登記簿に反映させることとなり、相続登記の申請義務を履行したことになります。
尚、この申出は、相続人中の1人からでも申出ができます。(申出の際の添付書類も申出人が相続人であることを戸籍謄本等を提出すればよく、相続人全員を把握するための戸籍謄本等全てを取り寄せる必要もありません。)
ただし、相続人申告登記により、相続による所有権移転登記をしたことにはならず、相続が発生したことを公示するだけですのでご注意ください。
- 4相続による土地の所有権移転登記手続について、下記のとおり一定の要件を満たせば、登録免許税がかからないケースがございます。(令和9年3月31日までの期限付き)
ただし、建物の相続登記は通常通り登録免許税がかかります。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないまま死亡した場合、その死亡した方の名義に相続登記を申請する際、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
- 土地の評価額が「100万円以下」の場合、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)尚、100万円以下かどうかは各土地ごとに判断します。土地全体の評価額ではありません。また、持分の相続の場合、評価額に持分を乗じた金額が100万円以下かどうかで判断することとなります。
- 表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記を申請する場合、登録免許税は非課税となります。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
- 52023年「空き家法改正」により従来、住宅用地には固定資産税の負担について優遇措置がとられておりましたが、空き家を放置したままにすると「管理不全空き家(例:屋根や柱、塀などが破損している。敷地内にゴミが散乱しているなど・・)と認定され、さらに放置すると「特定空き家(例:屋根や柱、塀などが破損していて倒壊の恐れがある。敷地内にゴミが散乱していて悪臭がするなど・・)」と認定されて固定資産税が6倍に上がってしまう可能性がございます。
よって、相続登記を速やかに行い、空き家を管理したり売却等処分をする必要があります。
- 6「相続登記の義務化」や「特定空き家に認定されて固定資産税の負担が増大するリスク」を考えて、生前に不動産を売却して現金化しておくというのも手段の一つです。
(居住用不動産の売却の場合、譲渡所得について最高3,000万円まで控除の特例が適用されます。)
居住用不動産を譲渡したときは、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除ができます。(居住用不動産の3,000万円控除の特例)
- 7親が施設に入っていて実家が空き家になっている状況で、空き家の放置リスクをなくしたいとお悩みの方・・「家族信託」という方法がございます。
実家を空き家のまま放置をしていると、老朽化により建物や塀が倒壊して近隣に迷惑がかかる危険性があったり(損害が出た場合、損害賠償請求をされる恐れがあります。)、「特定空き家」と認定されて固定資産税が最大6倍になることもございます。
そのような危険性を回避するために「家族信託」という方法がございます。
これは、親が健全な内に子に実家の管理や売却をする権限を与えて、万が一、親が認知症など判断能力がなくなっても、子が親に代わって空き家の管理や売却ができるというものです。
<スキーム>
委託者(実家を所有している方)・・親
受託者(実家の管理や売却を任された方)・・子
受益者(信託により利益をもらう方・今回で言えば、例えば、毎月一定の金額を生活費として親に支給するというケースなど)・・親
信託財産・・実家・金銭
信託終了事由・・親の死亡
信託終了時の残余財産の帰属権利者(財産をもらう方)・・子
詳細は、当HPの「家族信託」の項目に掲載しております。
- 82026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が運用されます。
所有不動産記録証明制度とは、「個人がどこにどのような不動産を所有しているのか」を法務局に請求することにより一括で検索できて、まとめて一覧できる証明書を発行してもらう制度です。
この証明書により、生前に財産整理をしたいという方や、相続登記を申請する方には必要な不動産を把握しやすくなり、スムーズに相続手続きができるようになります。
また、将来的に所有者不明土地の問題を解消できるようになると考えます。
(請求者)本人、相続人
(請求方法)法務局窓口もしくはオンラインにより請求
(手数料)1通につき1,600円(法務局窓口で請求する場合)
(証明書の記載内容)登記簿上の氏名及び住所と一致する不動産が一覧できます。
<問題点>
①登記簿上の氏名及び住所と一致しない場合、証明書に反映されません。そうなると、住所変更や氏名変更があった場合、事前に住所変更登記や氏名変更登記を行う必要があります。
②未登記建物は証明書に反映されません。
未登記建物を所有されている場合、「所有不動産記録証明書」と「名寄帳」を併用して調査する方法が考えられます。(「名寄帳」には未登記建物も反映されます。)
③プライバシー保護のため、請求者は本人及び相続人に限定されています。
「相続登記申請手続き」は「全国対応」です。
当事務所では、「なかなか相談できる専門家が身近にいなくて・・。」とお悩みの方から御連絡をいただくことが非常に多いです。どのような御相談内容でも結構です。とりあえずお電話もしくはメールで御相談ください。
| 遺 産 分 割 協 議 ・ 調 停 ・ 審 判 が あ っ た か ? | |
|---|---|
| あり ↓ | なし ・遺言書について詳しくお知りになりたい方は、こちらから |
| 共 同 相 続 登 記 の 有 無 | |
| あり | なし |
| 「遺産分割」による所有権移転登記 令和5年4月1日以降~ 「遺産分割」による所有権更正登記が可能 (不動産を取得した方の単独申請) | 「相続」による所有権移転登記 |
| (相続不動産の売買を御検討される方は) 「相続不動産の売却」 | (相続不動産の売買を御検討される方は) 「相続不動産の売却」 |
\\
共同相続登記をやっていない状態で遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を取得した場合
被相続人死亡と同時に、相続人全員の共同相続登記をせずに直接、単独で「相続」を原因とする所有権移転登記を申請します。
1⃣ 原則 遺産分割協議による相続登記の必要書類一覧表(被相続人(亡くなられた方)・相続人)
<被相続人(亡くなられた方)に必要なもの>
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等
(被相続人の出生時~死亡時までのもの) - 住民票除票もしくは戸籍の附票(被相続人の死亡時の住所が分かるもの) ただし、上記の書類が役所の保存期間経過により取得できない場合、(1)権利証もしくは(2)納税通知書(原本)と上申書(不動産登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることは間違いない旨を相続全員で証明する形で、この書面に相続人全員の実印と印鑑証明書を添付します。)で代替できます。 尚、登記簿上の住所が戸籍謄本上の本籍地と一致している場合、2の書類は不要です。
- 固定資産税評価額証明書(登録免許税の計算のため)
- (令和5年12月18日法務省通達 「被相続人の同一性に関する不動産登記事務の取り扱いについて」)
一定の要件を満たせば、被相続人の登記簿上の住所と除票上の住所が一致していなくても「上申書の提出が不要」となる取り扱いとなりました。
①「被相続人の除票または戸籍の附票」及び「固定資産税評価額証明書または納税通知書」並びに「不在籍不在住証明書」が提供されていること
②「登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名」が「納税通知書等に記載された不動産の表示・納税義務者の氏名」と一致していること
③「納税通知書等に記載された納税義務者の住所・氏名」が「除票等に記載された被相続人の住所・氏名」と一致していること
③「除票に記載された被相続人の本籍及び氏名」が「被相続人の戸籍謄本等に記載された本籍及び氏名」と一致していること
<相続人に必要なもの>
- 現在の戸籍謄本
- (遺産分割協議をした場合)印鑑証明書
- 住民票(不動産を相続する者のみで可・マイナンバーの記載のないもの)
- (遺産分割協議をした場合)遺産分割協議書
2⃣ 遺産分割調停もしくは遺産分割の審判によって相続登記を申請する場合の必要書類
- 遺産分割調停調書もしくは遺産分割審判書(確定証明書付)
- 被相続人の除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が違う場合、住所移転の経緯が分かるもの)
- 相続人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
- 固定資産税評価証明書(登録免許税の計算のため)
<相続登記を速やかに進めるためのポイント>
(1)「法定相続情報一覧図」の利用を御検討ください。
「相続登記」・「銀行や証券会社での承継手続き」・「相続税の申告」といったお手続きを進める前に、戸籍謄本等資料と相続関係一覧図を管轄の法務局に提出して、登記官に相続関係に間違いない旨の認証をもらった書面(「法定相続情報一覧図」といいます。)を利用すると、お手続きがスムーズに進みます。
法定相続情報一覧図の提出のみで、相続手続きをする際に上記の戸籍謄本などの相続関係書類を逐一提出することもございません。しかも発行料は無料です。
(2)「戸籍の広域交付制度」の利用を御検討ください。
2024年3月から本籍地以外での市区町村でも戸籍謄本を発行できる「戸籍の広域交付」制度が始まりました。
これは、相続人本人が郵送でなく役所の窓口で申請する必要がございますが、お近くに役所で戸籍謄本をまとまて取得できるになり、かなり御負担が軽減されました。
(3)「名寄帳」を取り寄せて物件漏れがないように調査してください。
相続対象物件の漏れがないよう事前に「名寄帳(市区町村が所有者が所有している不動産の情報をまとまたものです。)」を取り寄せて調査することをおすすめします。
固定資産税の納税通知書中に、公衆用道路部分など課税されない物件が記載されないケースがあり、全ての不動産について相続登記をしたつもりが、後日一部の不動産が漏れていたというケースがございます。
<従来>
相続することになった相続人を登記権利者(登記をすることで権利をもらう人のことをいいます。)・他の相続人全員を登記義務者(登記をすることで権利を失う人のことをいいます。)として共同で「遺産分割」を原因とする共有持分移転登記を申請します。
必要書類
登記原因証明情報(遺産分割協議書・調停調書正本・審判書正本)
権利証(登記識別情報)
登記義務者の印鑑証明書(3ヶ月内)
登記権利者の住所証明書(マイナンバーの記載のないもの)
不動産の固定資産税評価証明書
<令和5年4月1日以降>相続登記義務化に伴い、速やかに登記申請ができるように「不動産を取得した者の単独申請による所有権更正登記」が可能となりました。
ただし、利害関係人の承諾書が得られない場合もあるので、従来の「所有権移転登記」によることもできます。
(登記権利者による所有権更正登記ができるケース)
以下の場合、不動産を取得した者(登記権利者)が単独で所有権更正登記の申請ができるようになりました。
①遺産分割(協議・調停・審判)により、不動産を取得した時
②他の相続人が相続放棄したことにより、残りの相続人が新たに権利を取得した時
③「特定の者に相続させる」旨の遺言書(特定財産承継遺言といいます。)が発見され、所有権を取得した時
④相続人に対する遺贈により、所有権を取得した時
(登記原因)
①遺産分割による更正・・「原因 年月日遺産分割(日付は協議成立日・調停成立日・審判確定日)」
②相続放棄による更正・・「原因 年月日相続放棄」(日付は相続放棄申述受理日)
③特定財産承継遺言による更正・・「原因 年月日特定財産承継遺言」(日付は、遺言者死亡日が原則)
④遺贈による更正・・「原因 年月日遺贈」(日付は、遺贈者の死亡日が原則)
(登記手続に必要な書類)
・登記原因証明情報(遺産分割の場合、協議書(印鑑証明書付)・相続放棄の場合、相続放棄申述受理証明書及び戸籍謄本など・特定財産承継遺言の場合、遺言書(検認済の自筆遺言証書や公正証書遺言)・遺贈の場合、遺言書(検認済の自筆証書遺言や公正証書遺言))
・司法書士に依頼する場合、委任状
・利害関係人(例:法定相続登記後に相続人の1人の持分について設定した抵当権者など)の承諾書
*登記権利者の単独申請なので、登記義務者(他の相続人)の登記識別情報通知書や印鑑証明書不要です。
(登録免許税)
不動産1個につき1000円
- 4
遺言書がある場合
<相続登記の必要書類>
- 検認済の自筆遺言書または遺言書情報証明書または公正証書の遺言書
- 被相続人の除票
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍簿謄本
- 相続人の住民票(マイナンバーなしのもの)
- 固定資産税評価証明書
相続が発生してから抵当権の抹消をしたいとき、どうすればいいの?
「所有権の相続登記」⇒「抵当権の抹消登記」という順番で登記申請をする流れとなります。
持ち家の方は、通常、「民間の住宅ローン」を利用されて土地と建物に抵当権を設定しているケースが多いです。
その場合、住宅ローンとセットで「生命保険」がかけられているので、抵当権設定者(土地・建物の所有者)が亡くなると、生命保険で残りのローンを支払って抵当権も抹消されることになります。
このケースでは、抵当権の抹消登記をするだけでなく、その前提として土地・建物の所有権の相続登記もしなければなりません。
登記の順番としては1.「所有権の相続登記」⇒2.所有権の相続登記の名義人と抵当権者の共同申請で「抵当権の抹消登記」という流れになります。
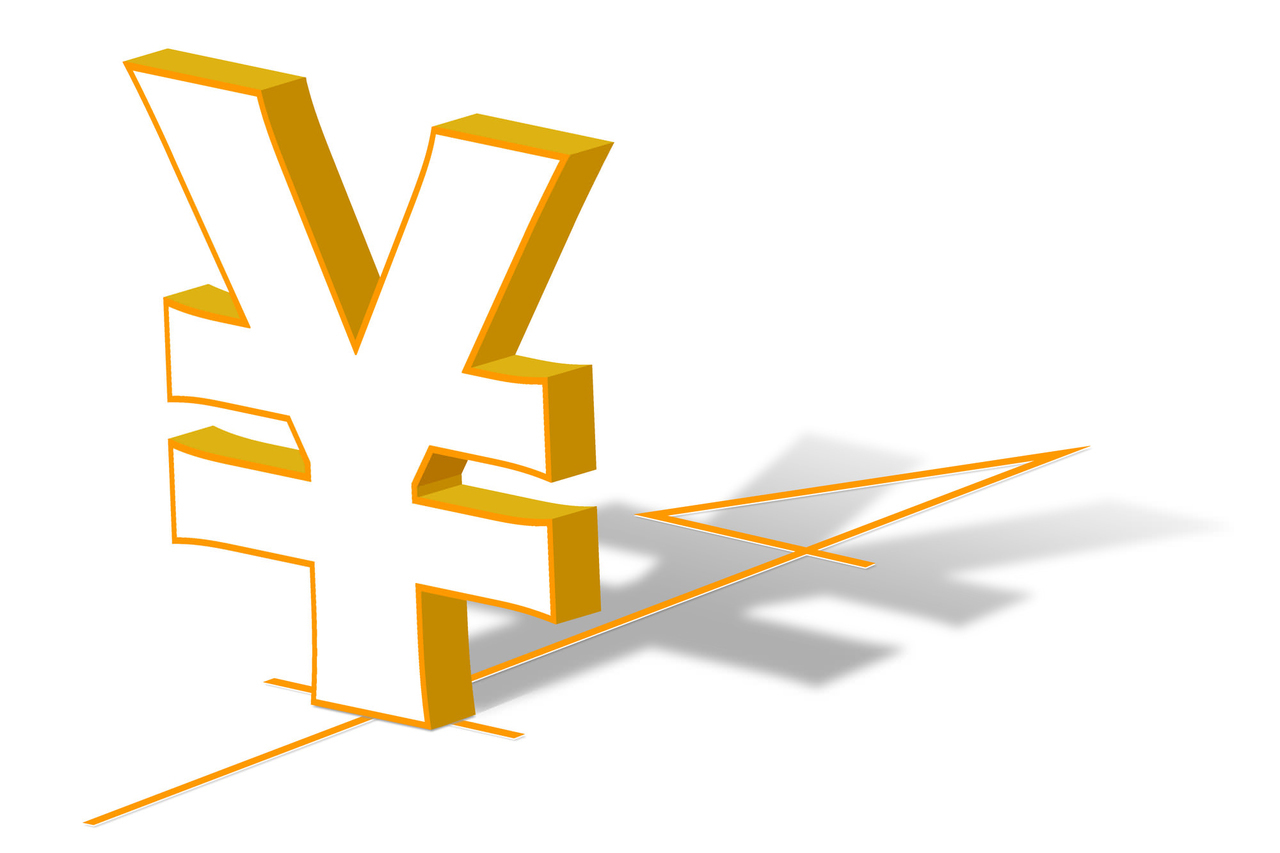
登録免許税 不動産の評価額の1000分の4
尚、各土地ごとの評価額が100万円以下の場合、登録免許税が非課税となります。(令和9年3月31日まで)
それに加え、司法書士の報酬・実費を含め通常だと約10万円から20万円位です。(事案の複雑度によります。)
当事務所では、ほとんどの案件で「オンライン申請」を行っておりますので、「日当」なども原則としてかからずにお費用を安く抑えることができます。
「相続登記申請手続き」は「全国対応」です。
不動産の謄本・固定資産税評価証明書(もしくは納税通知書)の資料があれば、ある程度の御見積書の御案内もできます。御見積もりは無料です。
尚、自宅ご購入時に住宅ローンとセットで「生命保険」がかけられているケースが多いので、その場合、抵当権設定者(土地・建物の所有者)が亡くなると、生命保険で残りのローンを支払って抵当権も抹消されることになります。
このケースでは、抵当権の抹消登記をするだけでなく、その前提として土地・建物の所有権の相続登記もしなければなりません。
登記の順番としては1.「所有権の相続登記」⇒2.「抵当権の抹消登記」という流れになります。
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
- 費用に関するお問合せ
- 手続に関するお問合せ
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
<h5>司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット</h5>
<strong>・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット1:時間や手間を省くことができる</strong>
登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度ですから、その内容を変更する手続きは法律で細かくルールが決められています。相続登記も例外ではなく、必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。実際に、相続登記手続きに必要な書類を不足なく集めて、正確な申請書を作成するには、相当な時間と労力が必要です。「苦労して必要書類を集めて申請したが、書類が不足していて登記できなかった」、「自分で申請してみたが間違いが多すぎて申請をやり直すように言われてしまった」などと途中で挫折してしまうケースも少なくありません。忙しくてなかなか手続きが進まない場合や手続きに不安がある場合は、最初から司法書士に相談したほうが余計な時間や手間をかけずに済みます。
<strong>・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット2:ほかの相続手続きも合わせて依頼できる</strong>
相続手続きにおいて、司法書士が業務として行えるのは相続登記だけではありません。戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成はもちろんのこと、預貯金の解約払戻手続きや有価証券の名義変更なども行うことができます。依頼者の方から、「相続登記だけをお願いするつもりだったけれど、ほかの相続手続きも一緒に依頼することができてとても助かりました」という声をいただくことも少なくありません。
<strong>・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット3:相続人の特定が正確にできる</strong>
不動産の所有者が死亡したときに相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合の「代襲相続」や、相続登記をする前に相続人が亡くなってしまった場合の「数次相続」など、相続関係が複雑なときは司法書士に相談したほうが安心です。相続人の特定には、戸籍謄本の読み解きが必要ですが、代襲相続や数次相続の場合には戸籍謄本の通数も膨大になります。すべての戸籍謄本をしっかり読み解き、相続人を正確に特定するには一定の知識と経験が必要不可欠と言えます。
<strong>・司法書士に相続登記手続きについて相談するメリット4:見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる</strong>
たとえば、一戸建ての実家の相続登記をする場合に、土地と建物が一つずつとは限りません。敷地が2筆以上の土地に分かれていることもありますし、建物についても物置や離れが母屋とは別に登記されていることもあります。そして、最も見落とされがちなのが私道やごみ置場などの共有持分です。分譲住宅地の場合、道路が私道になっていて周辺住民でその私道の所有権を共有していることがあります。ごみ置場や集会所などの共用施設についても同様です。私道などの共有持分について相続登記が漏れていたとしても、日常生活で困ることはありませんが、売却や建て替えを行うときに登記漏れが問題になることがあります。司法書士は、相続人から申し出のあった不動産だけでなく、評価証明書や名寄帳、亡くなった人の権利証などから不動産を特定しますので、登記漏れを防ぐことができます。
<h5>相続登記を司法書士に相談すべきケース</h5>
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース1:仕事などで平日の日中に時間がとれない</strong>
相続登記を申請する法務局の開庁時間は、平日8時30分から17時15分までです。仕事などをしている場合、自分で相続登記を行うには、平日の日中にある程度まとまった時間がとれないと難しいかもしれません。「自分でやるつもりで準備していたけれど、平日に時間がとれず気がついたら1年以上も経ってしまった」と依頼に来る方も少なくありません。
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース2:相続した不動産をすぐに売却したい(担保に入れたい)</strong>
相続した不動産を売却して代金を相続人間で分配する場合や、相続税の納税資金を金融機関から借りる場合は、できるだけ速やかに相続登記を行うべきです。売却時には買主への所有権移転登記、借入時には抵当権など担保権設定登記を行いますが、いずれも前提として相続登記が必要だからです。相続登記が遅れるとあとの売却や借入れにも大きく影響しますので、司法書士に依頼してスムーズに進めたほうがよいでしょう。
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース3:相続した不動産が複数ある</strong>
亡くなった人が自宅以外に賃貸マンションや駐車場、山林、田畑など複数の不動産を所有していた場合も注意が必要です。不動産の所在地が散らばっていて管轄する法務局が分かれる場合には、物件ごとに別々の法務局に申請する必要があります。不動産の数が多いと登記漏れを起こす可能性も高くなりますので、司法書士に依頼するほうが確実で安心でしょう。
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース4:音信不通の相続人がいる</strong>
音信不通の相続人がいる場合には、不動産を引き継ぐ人を決める遺産分割協議ができません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた場合には無効になってしまうからです。このような場合には、不在者財産管理人の選任手続きが必要になります。家庭裁判所で音信不通の相続人(=不在者)の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人が遺産分割協議に参加します。司法書士は家庭裁判所に提出する不在者財産管理人選任申立書の作成も業務として行うことができます。
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース5:未成年の相続人がいる</strong>
未成年の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行う前提として特別代理人を選任する必要があります。たとえば、自宅の所有者である夫が死亡し、妻と15歳の子どもが相続人だった場合、妻が単独で自宅を引き継ぐには、相続人である妻と子の間で遺産分割協議を行うことになります。この場合に、親権者である妻と未成年の子の間で遺産分割協議を行うことは利益相反取引(親が得をすると子が損となり、子が得をすると親が損になる取引)に該当します。そのため、親権者に代わる特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、妻と特別代理人の間で遺産分割協議を行う必要があるのです。特別代理人の選任を行う場合の申立書作成も司法書士の業務の一つです。
<strong>・相続登記を司法書士に相談すべきケース6:相続人に疎遠な人がいる</strong>
亡くなった人に前妻(夫)との間の子がいる場合や遠縁の親族が相続人になる場合など、ほとんど面識のない相続人同士が連絡を取り合い、相続登記を行うのは非常に負担が大きい作業です。このような場合に中立的な第三者である司法書士が連絡役になることで、相続人同士が過度な負担を感じることなく相続登記を進めることができます。ただし、司法書士は相続人同士の紛争を解決したり、特定の相続人の代理人としてほかの相続人と交渉したりすることはできない点に注意が必要です。相続登記の前提で相続人間に対立関係が生じてしまった場合には弁護士に依頼することになります。出展:相続登記 まずは司法書士に相談を 依頼すべきケースや費用、選び方を解説
<h5>司法書士に相続登記手続きについて相談するときの司法書士の選び方</h5>
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント1:相談したい分野の経験が豊富かどうか</strong>
司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除き、正当な理由なく依頼を断ってはいけないと法律で決められています。そのため、相続登記などの依頼はすべての司法書士が対応できる前提となっています。それでも、すべての事務所が相続の手続きを得意としているわけではありません。なかには相続分野の案件をあまり受託したことがない事務所もあります。ホームページの内容を確認したり、実際に電話やメールで問い合わせをしたりして、経験豊富な事務所に相談予約をしましょう。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント2:親身に話を聞き、丁寧な説明と的確なアドバイスをしてくれるかどうか</strong>
相続登記手続きの相談に行き、実際に依頼するかどうかを決める際に重視すべき点は、相談者の話をしっかり聞いてくれるかどうかです。なかには最初から主導権を握り、法律知識を駆使して話を進めようとする司法書士もいます。わかりやすい言葉を使い、相談者目線に立って話を聞いてくれるかどうかを見るようにしてください。そのうえで、相性や話しやすさ、質問のしやすさ、説明の丁寧さなど、相談のなかで前向きに感じたものを重視してください。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント3:対応が早いかどうか</strong>
相続登記手続きの場合、どの司法書士に相続登記手続きについて相談しても、登記記録に記載される内容は同じです。だからこそ、話しやすい、信頼できるといった要素に加えて、いかにスピーディーに対応してもらえるか、こちらの連絡や要望に素早く対応してもらえるかといった要素は、司法書士を選ぶうえで重要なポイントです。相談予約や問い合わせをした際の対応スピードも一つの指針になります。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント4:足を運びやすい立地に事務所があるかどうか</strong>
一般的には、司法書士に相続登記手続きについて依頼する前に直接会って相談し、その後は電話やメール、郵便などでやりとりをするケースが多いです。最近では相続登記手続きについて、リモート相談で対応している司法書士事務所もありますが、できれば一度は司法書士と直接、対面して相談するのがよいでしょう。司法書士の人柄や雰囲気など、実際に会ってみないとわからない部分もあるためです。その意味では、相続登記手続きについて相談するときは、自宅や勤務先から行きやすい場所にある事務所を探すのもポイントの一つです。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント5:土日祝日や夜にも対応してくれるかどうか</strong>
司法書士事務所の多くは、土日祝日を休業日としています。また、18時ごろに営業を終了する事務所も多く、いわゆるビジネスタイムに働いている人にとっては訪問するのが難しい場合があります。しかし、司法書士事務所のホームページに記載されている営業時間の項目を見ると、土日祝日を休みとしつつも「ご希望があれば対応します」としている事務所もあります。相続登記手続きについて希望の日時に相談に応じてもらえるか、電話やメールなどで問い合わせてみるとよいでしょう。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント6: 料金体系がわかりやすくリーズナブルかどうか</strong>
司法書士の報酬は法律などで決められた一律の基準はなく、それぞれの事務所が自由に報酬基準を定めています。とはいえ、おおよその相場はあるため、事務所によって大幅に変わることはそう多くありません。ただし、相続登記手続きについて最初の段階で見積もりを提示してもらえるかどうかは、依頼をするうえで重要です。相続登記手続きについて、相談の段階でできるだけ具体的な資料を持参し、正確な見積もりを出してもらうようにしましょう。
<strong>・相続登記手続きについて相談するときのポイント7:弁護士や税理士と連携しているかどうか</strong>
相続登記手続きの相談の場合、司法書士だけで完結するケースばかりではありません。遺産分割の話し合いがまとまらない場合や相続争いがある場合には、弁護士の力が必要です。また、遺産総額がある程度大きく、相続税の申告が必要となる場合には税理士の力が必要となります。このような場合に、それぞれの専門家を自分で探すよりも、依頼した司法書士から関係性のある専門家に話をつないでもらうほうが、相続手続きをスムーズに進められます。遺産分割がまとまらないケースや、相続税の申告が必要などの課題が最初から明らかなケースでは、司法書士に相談する際にそれぞれの専門家につないでもらえるかを確認しておくとよいでしょう。
<h5>相続登記手続きについて相談するときの司法書士の探し方</h5>
<strong>・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント1:ホームページやSNSから探す</strong>
ホームページを開設している司法書士事務所は多くあります。ほとんどのホームページに取り扱い業務や報酬、司法書士の紹介が記載されているため、おおよその雰囲気をつかむことができます。また、Instagram(インスタグラム)やブログなどで情報発信をしている事務所もあるため、相続登記手続きについて相談するときは、それらも参考にするとよいでしょう。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント2:司法書士ポータルサイトを活用する</strong>
「相続会議」などのポータルサイトには相続登記手続きに強い司法書士事務所が多数登録されています。「相続会議」はエリアや相談内容ごとに検索できるため、自分に合った司法書士事務所を簡単に見つけることができます。簡単に自宅近くの相続登記手続きに強い司法書士を探したい場合は、このようなポータルサイトを利用するのもよいでしょう。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント3:知人や友人に紹介してもらう</strong>
過去に相続登記手続きについて司法書士に依頼した経験を持つ知人や友人がいる場合は、相続登記手続きについて依頼した感想を聞いてみて、場合によっては紹介してもらうのもよいでしょう。司法書士へ相続登記手続きについての依頼を経験した人の生の声ですので、かなり信憑性の高い情報であることは間違いありません。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント4:司法書士会に問い合わせる</strong>
各都道府県には司法書士が会員として所属する司法書士会が設置されています。電話やメールなどで司法書士会に、相続登記手続きについて直接問い合わせて、自分の希望する条件に合う司法書士を紹介してもらう方法もあります。ただし、司法書士会がすべての司法書士の特徴までを把握しているわけではありません。司法書士会のホームページにある会員検索ページから自分で検索するのと、得られる情報量はあまり変わらないかもしれません。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士の探し方のポイント5:無料相談を活用し、複数の事務所に足を運ぶ</strong>
司法書士事務所では、相続登記手続きについて、初回の相談を無料としている場合が多いため、まずは事務所に直接電話やメールをして相談予約をしてみるのも一つの方法です。また、司法書士会や自治体が主催する各地の無料法律相談を利用して、相続登記手続きについて、実際に司法書士と対面で話をしてみるのもよいでしょう。
<h5>相続登記手続きについての司法書士の選び方で後悔しないための注意点</h5>
<strong>・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント1:中小規模の事務所も検討する</strong>
大規模な事務所であれば、同じ事務所内であっても資格者ごとに経験や知識、力量に大きな差がある場合があります。そのため、ホームページを確認し、内容に納得したうえで訪問しても、相続登記手続きについて、実際に話を聞いてみると期待したほど頼りがいがないケースもあります。相続登記手続については、経験豊富なベテランが中心となって対応してくれる小さな事務所を探すのも一つの方法です。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント2:口コミやレビューを確認する</strong>
相続登記手続きについて、司法書士事務所の口コミやレビューが確認できるのであれば、それらを司法書士選びの参考にするのもよいでしょう。ただし、どんな司法書士であっても、すべての人の好みに合うのは難しいと考えられます。口コミやレビューは個人の主観にすぎないため、あくまで参考程度にとどめ、実際に会って相続登記手続きについての話を聞いた際の感触を大切にすることをお勧めします。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント3:費用の安さだけを選考基準にしない</strong>
相続登記手続きについてホームページで確認できる報酬額は、報酬の総額が記載されているものばかりではありません。たとえば「相続登記4万円」と書かれていても、それは申請代理分の報酬であり、通常は遺産分割協議書作成報酬や戸籍謄本の取り寄せ代行報酬などが加算されます。4万円だけ払えばいいと思っていたら、最終的な報酬は10万円を超えてしまったというケースもあります。このように、相続登記総額が安く設定されていても、報酬額だけを見てすぐに依頼をするのは避けたほうが良いと言えます。いくら安くても対応が遅かったり、仕事が雑だったりしたら元も子もありません。しっかりと話を聞いて相性や説明のわかりやすさなどを確認し、費用を含めて総合的に判断することをお勧めします。
<strong>・相続登記手続きについての司法書士選びで後悔しないためのポイント4:相談内容と司法書士の対応業務が一致しているかを確認する</strong>
自分が抱えている問題と司法書士事務所の得意分野が一致しているかどうかも、問い合わせ段階で確認しておきましょう。たとえば相続分野で言えば、司法書士が取り扱うのが最も多いのが相続登記です。次に、相続放棄の書類作成など、裁判所に提出する書類の作成業務があります。そのほかにも、相続財産となっている預貯金などを相続人に承継させる手続きの代行業務、遺言作成の援助業務などがあります。どの司法書士事務所でも比較的よく対応している業務もあれば、ほとんど経験がない業務もあります。
<h5>まとめ</h5>
司法書士に相続登記手続きについて相談や依頼をする際は、相続登記手続きについて精通しているかどうか、親身になって丁寧かつスピーディーに対応してくれるかどうか、弁護士や税理士と連携しているかなどのポイントを基準に選ぶことが大切です。また、相続登記手続きについての司法書士の探し方には、司法書士事務所のホームページやSNSを参考にする方法や、相続登記手続きについて実際に依頼したことのある友人、知人から情報を得る方法、司法書士会や法テラスに問い合わせる方法などがあります。まずはこれらのポイントに沿って、相続登記手続きについて無料相談を通して実際に司法書士に会い、自分でさまざまな面を確認したうえで、信頼して任せられると思える司法書士に依頼しましょう。出展:司法書士の選び方と探し方 経験、人柄、費用、立地など見極めるポイントを解説
<h4>さいたま市の街情報</h4>
<h5>さいたま市にある観光スポット</h5>
<strong>【吉祥寺】:埼玉県さいたま市緑区大字中尾1410</strong>
最寄り駅【東浦和駅】:埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目
最寄りIC【川口西IC】:埼玉県川口市伊刈
吉祥寺は、さいたま市緑区大字中尾1410にあります。吉祥寺の境内は緑が多く、落着いた雰囲気のある寺院です。829年、慈覚大師円仁が開山した天台宗のお寺です。ご本尊は、十一面観世音菩薩です。山門は300年以上(さいたま市指定文化財)歴史があり、人気の寺院です。
<strong>【総持院】:埼玉県さいたま市緑区南部領辻2944</strong>
最寄り駅【浦和美園駅】:埼玉県さいたま市緑区美園4丁目
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
総持院は、さいたま市緑区南部領辻2944にあります。総持院は、自然豊かでのどかな真言宗智山派の寺院です。参道や鐘楼門、本堂とが立派で人気の寺院です。境内の牡丹も人気で、開花時期はに多くの参拝者が訪れる穴場的寺院です。
<strong>【さいたま市立浦和博物館】:埼玉県さいたま市緑区三室2458</strong>
最寄り駅【北浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区4丁目4
最寄りIC【さいたま見沼IC】:埼玉県さいたま市緑区三浦
さいたま市立浦和博物館は、さいたま市緑区三室2458にあります。さいたま市立浦和博物館は、埼玉県師範学校鳳翔閣の中央部外観を復元した建物で、令和4年2月10日に、良好な景観形成の核となる建造物であると評価され、さいたま市景観重要建造物第10号に指定されました。
<strong>【浦和くらしの博物館民家園】:埼玉県さいたま市緑区大字下山口新田1179-1</strong>
最寄り駅【東浦和駅】:埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
浦和くらしの博物館民家園は、さいたま市緑区大字下山口新田1179-1にあります。浦和くらしの博物館民家園は、さいたま市内の最古の民家や建造物などを、移設・復元し展示されている施設です。当時実際に使われていた道具などを使って、昔の人々の生活を体験できます。
<strong>【さいたま市園芸植物園】:埼玉県さいたま市緑区大字大崎3156-1</strong>
最寄り駅【浦和美園駅】:埼玉県さいたま市緑区美園4丁目
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
さいたま市園芸植物園は、さいたま市緑区大字大崎3156-1にあります。さいたま市園芸植物園は、緑区の国道463号線、クリーンセンター大崎(清掃工場)の北側にある、無料で入れる植物園です。花木園、見本庭園に、花き展示温室があります、整備された遊歩道沿いに、季節のお花が咲いていて楽しめます。
<strong>【武蔵一宮氷川神社】:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407</strong>
最寄り駅【北大宮駅】:埼玉県さいたま市大宮区土手町3丁目
最寄りIC【新都心西出入口】:埼玉県さいたま市大宮区
武蔵一宮氷川神社は、さいたま市大宮区高鼻町1-407にあります。武蔵一宮氷川神社は、2000年以上の歴史をもつといわれ、大いなる宮居として、大宮の地名の由来にもなった日本でも指折りの古社です。武蔵一宮として関東一円の信仰を集め、初詣には多くの参拝客で賑わいます。また、毎年5月には境内で恒例行事の大宮薪能が開催されます。
<strong>【鉄道博物館】:埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目47</strong>
最寄り駅【鉄道博物館駅】:埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目
最寄りIC【新都心西出入口】:埼玉県さいたま市大宮区
鉄道博物館は、さいたま市大宮区大成町3丁目47にあります。鉄道博物館は、様々な電車が展示されていて、テンションが上がります。館内の電車が展示されている場所は、少し薄暗いです。電車の中には、実際に入れたり、食事ができる電車もあり、他では体験できないことがここでは体験できます。
<strong>【別所沼公園】:埼玉県さいたま市南区別所4丁目</strong>
最寄り駅【中浦和駅】:埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目1
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
別所沼公園は、さいたま市南区別所4丁目にあります。別所沼公園は、洪積台地である大宮台地の谷中に位置し、台地からの湧水などが低地にたまってできたと考えられています。沼は釣りも可能で、噴水や弁財天がある弁天島があります。沼の周囲にはメタセコイアやラクウショウが茂り、その間を抜けるように散歩コースやジョギングコースが設定されています。
<strong>【浦和競馬場】:埼玉県さいたま市南区大谷場1-8-42</strong>
最寄り駅【南浦和駅】:埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目37−2
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
浦和競馬場は、さいたま市南区大谷場1-8-42にあります。浦和競馬場は、住宅地の真ん中に位置し、のどかな雰囲気です。古き良き競馬場テイストが味わえます。浦和競馬場は、戦後に制定された競馬法に基づき、地方自治体の主催で日本で最初に開催された、歴史ある地方競馬の競馬場です。
<strong>【さいたま市文化センター】:埼玉県さいたま市南区根岸1-7-1</strong>
最寄り駅【南浦和駅】:埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目37−2
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
さいたま市文化センターは、さいたま市南区根岸1-7-1にあります。さいたま市文化センターのホール内はとても広く、収容人数は約2千人も入ります。歌声が遠くの席にもしっかり聞こえるような建物の作りでよいです。南浦和駅西口正面の道路をまっすぐ進み、突き当りの左手にあります。 とても分かりやすいです。 学校やバレエなどの発表会などによく使われているようです。
<strong>【調神社】:埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-25</strong>
最寄り駅【浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16−12
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
調(つき)神社は、さいたま市浦和区岸町3-17-25にあります。調神社は、サッカー浦和レッズの街だけあってツキを呼ぶ、勝ちを祈るのにふさわしい神社です。玄神社には鳥居がないことで有名ですが、奥の元本宮には小さいながら鳥居もあります。本来なら狛犬がいるべき場所に、うさぎの石像があることもユニークです。お守りや絵馬も、うさぎのデザインになっています。
<strong>【玉蔵院】:埼玉県さいたま市浦和区仲町2-13-22</strong>
最寄り駅【浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16−12
最寄りIC【浦和北IC】:埼玉県さいたま市桜区中島2丁目22
玉蔵院は、さいたま市浦和区仲町2-13-22にあります。玉蔵院は、真言宗豊山派の寺院です。読み方は「ぎょくぞういん」です。桜の名所として知られています。いつでも拝観でき、拝観時間は9時から16時までとなっています。
<strong>【埼玉県立近代美術館】:埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目30-1</strong>
最寄り駅【北浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区4丁目4
最寄りIC【浦和北IC】:埼玉県さいたま市桜区中島2丁目22
埼玉県立近代美術館は、さいたま市浦和区常盤9丁目30-1にあります。埼玉県立近代美術館は、北浦和駅から徒歩3分ほどの緑豊かな公園敷地内にあります。モネやピカソ、ルノワールなどの海外巨匠の絵画や近代日本画が、常設展示されています。館内にはグッドデザイン賞を受賞したいすが休憩スペースに置かれ、自由に座ることができます。
<strong>【浦和駒場スタジアム】:埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目1-1</strong>
最寄り駅【浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16−12
最寄りIC【さいたま見沼IC】:埼玉県さいたま市緑区大字三浦
浦和駒場スタジアムは、さいたま市浦和区駒場2丁目1-1にあります。駒場スタジアムは、21500人もの収容人数を誇るサッカースタジアムです。女子チーム・浦和レッズレディースが、現在も本拠地として使用している、地元に密着したスタジアムとして知られています。また、男子チームである浦和レッズも、2010年までホームスタジアムとして使用していました。
<strong>【うらわ美術館】:埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目5-1</strong>
最寄り駅【浦和駅】:埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16−12
最寄りIC【浦和北IC】:埼玉県さいたま市桜区中島2丁目22
うらわ美術館は、さいたま市浦和区仲町2丁目5-1にあります。うらわ美術館は、単体の建物ではなく、高層ホテルが入っている複合商業施設センチュリーシティの中にあります。展示内容は、特に優れているというほどのものはありませんが、文化都市としての浦和には必要な施設だと思います。
<strong>【埼玉スタジアム2002】:埼玉県さいたま市緑区中野田500</strong>
最寄り駅【浦和美園駅】:埼玉県さいたま市緑区美園4丁目
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
埼玉スタジアム2002は、さいたま市緑区中野田500にあります。埼玉スタジアム2002は、浦和レッズのホームグラウンドであり、日本代表の試合や、小学生から高校生の各年代の大会も開催しているので、サッカーファンには最高のスタジアムです。サブグラウンドも、人口芝と天然芝と充実の環境が整っています。
<strong>【氷川女体神社】:埼玉県さいたま市緑区宮本2-17-1</strong>
最寄り駅【東浦和駅】:埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目
最寄りIC【浦和IC】:埼玉県さいたま市緑区大門
氷川女体神社は、さいたま市緑区宮本2-17-1にあります。氷川女体神社は、自然豊かなお社です。 見沼自然公園も併設されていて、とても自然豊かです。神社の歴史は、2000年前の崇神天皇の頃に建立と言われていますが、奈良時代建立という説もあるようです。
<h5>【さいたま市にある災害時避難場所】(抜粋)</h5>
<strong>【さいたま市南区にある災害時避難場所】(抜粋)</strong>
・【大谷口公園】:埼玉県さいたま市南区大谷口5736-1
・【南浦和小学校】:埼玉県さいたま市南区白幡1丁目1-20
・【明花公園】:埼玉県さいたま市南区大谷口5732
・【岸中学校】:埼玉県さいたま市南区南本町2丁目25-27
・【別所沼公園】:埼玉県さいたま市南区別所4丁目12
・【沼影小学校】:埼玉県さいたま市南区沼影2丁目8-36
・【浦和南高校】:埼玉県さいたま市南区辻6丁目5-31
・【南浦和中学校】:埼玉県さいたま市南区辻6丁目1-33
・【文蔵小学校】:埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目16-29
・【西浦和小学校】:埼玉県さいたま市南区曲本1丁目3-5
・【辻小学校】:埼玉県さいたま市南区辻6丁目3-28
・【浦和大里小学校】:埼玉県さいたま市南区別所7丁目14-28
・【辻南小学校】:埼玉県さいたま市南区辻8丁目7-32
・【谷田小学校】:埼玉県さいたま市南区太田窪5丁目10-6
・【大谷場東小学校】:埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目13-54
・【大谷口小学校】:埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸24
・【善前小学校】:埼玉県さいたま市南区太田窪2500-1
・【大谷場小学校】:埼玉県さいたま市南区南浦和1丁目18-3
・【浦和別所小学校】:埼玉県さいたま市南区別所2丁目5-34
・【向小学校】:埼玉県さいたま市南区大谷口5437
・【内谷中学校】:埼玉県さいたま市南区内谷6丁目10-1
・【白幡中学校】:埼玉県さいたま市南区白幡2丁目18-13
・【埼玉大学教育学部附属中学校】:埼玉県さいたま市南区別所4丁目2-5
・【舟山公園】:埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目38
・【大谷場中学校】:埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目13-54
・【大谷口中学校】:埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸21
・【浦和競馬場】:埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目8-42
<strong>【さいたま市北区にある災害時避難場所】(抜粋)</strong>
・【前谷公園】:埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目8-5
・【三貫清水緑地】:埼玉県さいたま市北区奈良町57-1
・【日進北小学校】:埼玉県さいたま市北区日進町3丁目178
・【番場公園】:埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1435-1
・【松原公園】:埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目42
・【宮原公園】:埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目79
・【東宮原ぼうさい広場】:埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目125-1
・【宮原中学校】:埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目129
・【大宮別所小学校】:埼玉県さいたま市北区別所町42-1
・【農業機械研究部門】:埼玉県さいたま市北区日進町1丁目40-2
・【県立大宮中央高校】:埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目499-1
・【吉野公園】:埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目379-1
・【土呂公園】:さいたま市北区土呂町1丁目42
・【市民の森・見沼グリーンセンター】:埼玉県さいたま市北区見沼2丁目94
・【本郷第1公園】:埼玉県さいたま市北区本郷町890-1
・【きたまちしましま公園】:埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目859
・【うねうね公園】:埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1916-3
・【県立大宮ろう学園】:埼玉県さいたま市北区植竹町2丁目68
・【日進公園】:埼玉県さいたま市北区日進町1丁目311
・【つつじヶ丘公園】:埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目213
<h5>【さいたま市にある駅】</h5>
<strong>・【さいたま市岩槻区】</strong>
・東岩槻駅:さいたま市岩槻区東岩槻1丁目12-1・岩槻駅:さいたま市岩槻区本町3丁目1・浦和駅:さいたま市浦和区高砂1丁目16-12・北浦和駅:さいたま市浦和区北浦和3丁目3-5・与野駅:さいたま市浦和区上木崎1丁目1-1
<strong>・【さいたま市大宮区】</strong>
・大宮駅:さいたま市大宮区錦町630・鉄道博物館駅:さいたま市大宮区大成町3丁目89・さいたま新都心駅:さいたま市大宮区吉敷町4丁目57-3・北大宮駅:さいたま市大宮区土手町3丁目285・大宮公園駅:さいたま市大宮区寿能町1丁目130
<strong>・【さいたま市北区】</strong>
・土呂駅:さいたま市北区土呂町1丁目14・日進駅:さいたま市北区日進町2丁目881・宮原駅:さいたま市北区宮原町3丁目825・加茂宮駅:さいたま市北区宮原町1丁目305・東宮原駅:さいたま市北区宮原町2丁目109-7・今羽駅:さいたま市北区吉野町1丁目25-1・:吉野原駅:さいたま市北区吉野町1丁目404-2
<strong>・【さいたま市中央区】</strong>
・北与野駅:さいたま市中央区上落合2丁目3-1・南与野駅:さいたま市中央区鈴谷2丁目578・与野本町駅:さいたま市中央区本町東2丁目3-11
出展:ホームメイト・じゃらん・じゃらんネット・フォートラベル・スタディサプリ
無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
 求人情報を更新しました。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
登記をオンライン申請
で行ないませんか?
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
アクセス

(旧横田・福村司法書士事務所)
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
営業日
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
営業時間
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
業務エリア
さいたま市、蕨市、川口市他



