埼玉県さいたま市で、遺言相続・遺産相続でお悩みなら、福村司法書士事務所へお任せください。
さいたま市で相続登記・遺言書作成は
埼玉遺言相続・遺産相続相談所
<住所>〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番12号501号室
土日祝・時間外も柔軟に対応します
相続分の譲渡
<簡単まとめ:このページから分かること>
相続が発生して相続人全員で話しあう時に、自分の相続分を譲渡(売買や贈与)することで、遺産分割協議に参加しなくてよい方法について詳しく御案内しております。
実際に、相続人の一部が他の相続人へ相続分譲渡後、残りの相続人間で遺産分割協議を行って相続手続きを進めたケースがございます。
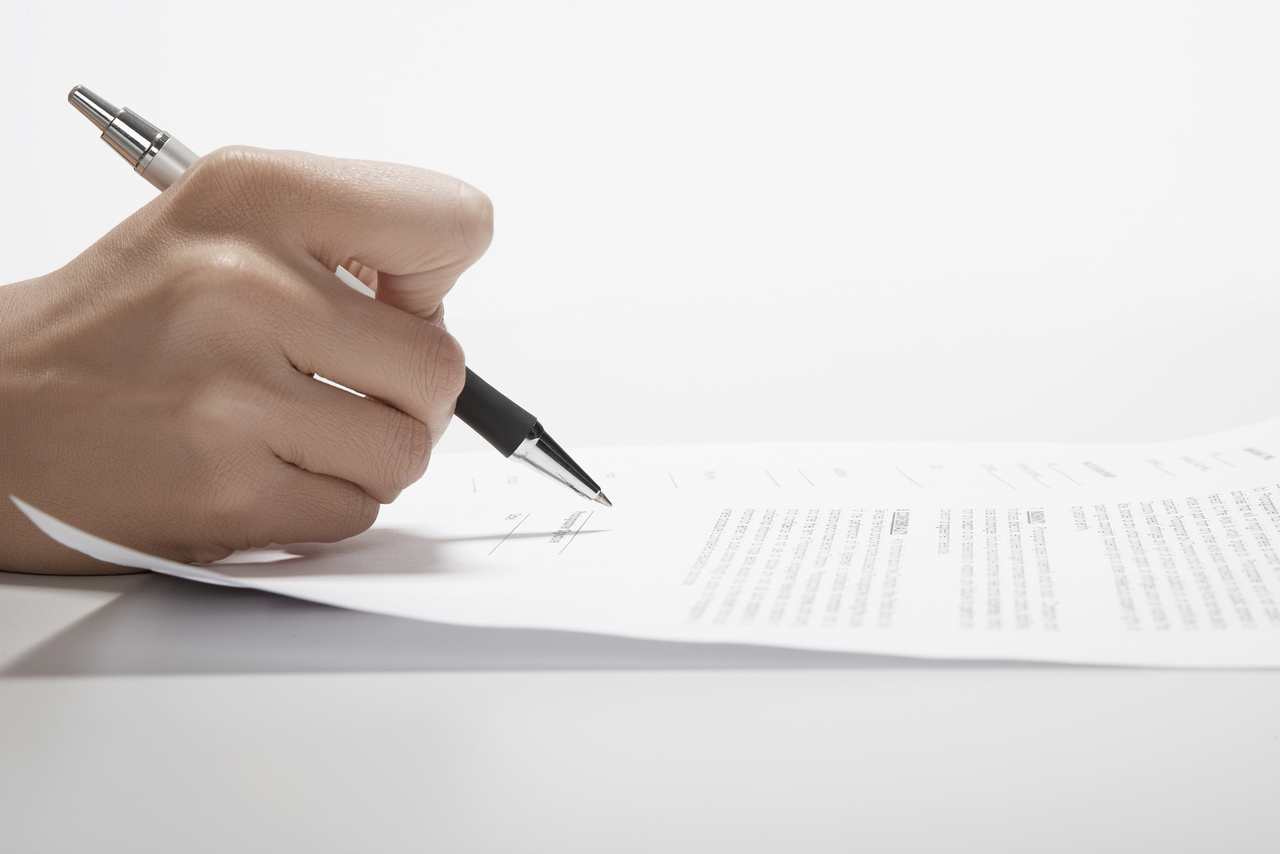
「相続分の譲渡」とは
遺産全体(積極財産・消極財産含む)に対して持っている「包括的持分」あるいは「相続人たる地位」を譲渡することをいいます。ただし、相続分を譲渡しても、相続債務は債権者の同意がないかぎり譲渡人は譲受人と連帯して弁済義務を負担することとなります。
家庭裁判所に「相続放棄の申立」をして相続放棄が受理されることで相続債務は免れることができます。(「相続放棄申立」については、こちらから)
ただし、実際は、相続分の譲渡の場合、以下のとおり税金上の問題がございますのでご注意ください。
(1)無償(贈与)の場合は、共同相続人間での相続分の譲渡であれば贈与税はかかりません。ただし、第三者に相続分を贈与した場合は、譲受人に贈与税がかかります。
(2)有償(売買)の場合は、譲渡人に対して譲渡所得税がかかります。ただし、相続人間での有償譲渡においては譲渡人に譲渡所得税は課税されません。
| 「相続分の譲渡を利用できるケース」 共同相続人間で遺産分割協議をする必要があるが、もめてしまうことが予想される場合、遺産分割協議前に相続分を他の相続人に事前に現金化して売りたい(もしくは、ただで贈与したい)ケースが考えられます。 当事務所でも、「一部の相続人が他の相続人に相続分譲渡後、残りの相続人間で遺産分割協議を行って相続手続きを進めたケース」はございます。 ・「遺産分割」について詳しくお知りになりたい方は、こちらから⇒ |
(相続分の譲渡ができる根拠)
相続分が共同相続人以外の第三者に譲渡された場合、その第三者が介入することにより遺産分割協議がまとまらないことがあります。そういった事情を解消するために、民法905条により、他の相続人が相続分を取り戻すことができるとしています。よって、相続分の譲渡に関する直接の規定はありませんが、この条文により相続分の譲渡が可能であるとされています。
| 相続分の取戻権(民法905条) 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 |
| <要件> 1.相続分の譲渡先が、「相続人以外の第三者」であること ⇒共同相続人間の譲渡の場合は不可 2.譲受人に対して相続分の価格及び譲渡に要した費用を支払うこと ⇒このときの相続分の価格とは「取戻権を行使する際の価格」となります。 3.譲渡されたときから「1か月以内」に行使すること ⇒取戻権を行使する際に、相続分の譲受人の承諾は不要です。 |
(譲渡できる時期)遺産分割をする前
(全部譲渡だけでなく一部譲渡も可能か)
相続分の譲渡は、相続分の全部譲渡だけでなく、一部の譲渡も可能(平成4年3月18日民三1404)
(譲渡の方式)譲渡の方法は口頭でも書面でもできますが、相続による所有権移転登記手続きなども考えると書面化した方がいいです。また、譲渡する際は、有償(相続分の売買)でも無償(相続分の贈与)でも構いません。
(譲渡の相手方)相続分の譲渡先は制限がなく、「共同相続人」または「共同相続人以外の第三者」でもいいです。尚、第三者に相続分を譲渡した場合は、相続財産上の権利義務が譲受人に移転するので、譲受人である第三者は遺産分割協議に参加ができることとなります。
登記手続き方法
<共同相続人間で相続分の譲渡をする場合>
1.共同相続登記をする前
例:相続人A、B、C、D(各相続分4分の1)
AがBに相続分(相続分4分の1)を譲渡
相続人B、C、D(B相続分4分の2・C相続分4分の1・D相続分4分の1)
相続人B、C、D間で遺産分割協議をして「Bが不動産を取得する」旨話し合いがまとまる。
直接、B名義に相続登記が可能
<添付書類>
相続証明書、BCD間の遺産分割協議書、Aの相続分譲渡証明書(実印押印して印鑑証明書添付<期間制限なし>)
<関連するケース>
相続人A、B、C、D間で遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所で遺産分割調停の申立後、相続人のうちのCDが相続分を相続人Aに譲渡して、AB間で「Aが不動産を取得する」旨の調停が成立した場合
相続を証する書面として遺産分割調停中に「CDが相続分を相続人Aに譲渡した」旨の記載があれば、それ以外に相続分を譲渡したことを証する書面を添付せずに、A名義に相続登記が可能
2.共同相続登記をした後
例:相続人A、B、C、D(各相続分4分の1)名義で相続登記
AがBに相続分(相続分4分の1)を譲渡
相続人B、C、D(B相続分4分の2・C相続分4分の1・D相続分4分の1)
相続人B、C、D間で遺産分割協議をして「Bが不動産を取得する」旨話し合いがまとまる
「遺産分割」を原因としてACD持分全部移転登記が可能
この場合、登記権利者がB 登記義務者がACDとする共同申請で行う。
<添付書類>
BCD間の遺産分割協議書、Aの相続分譲渡証明書(実印押印して印鑑証明書添付<期間制限なし>)
ACDの権利証(登記識別情報)、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
Bの住民票(マイナンバーの記載のないもの)
<共同相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合>
1.共同相続登記をする前
例:相続人A、B、C(各相続分3分の1)
Aが「第三者C」に相続分(相続分3分の1)を譲渡
⇒共同相続人以外の第三者に相続分の譲渡をしても、被相続人から直接、第三者への所有権移転登記はできない(登記研究491号)
法定相続でABC各3分の1名義で相続登記
Aから第三者Cに「相続分の売買(もしくは贈与)」を原因とするA持分全部移転登記
2.共同相続登記をした後
<遺産分割協議をしないケース>
例:相続人A、B、C(各相続分3分の1)名義で相続登記
Aが第三者Dに相続分(相続分3分の1)を譲渡
AからDへ「相続分の売買(もしくは贈与)」を原因とするA持分全部移転登記を行う。
<Dの単有とする遺産分割協議をしたケース>
例:相続人A、B、C(各相続分3分の1)名義で相続登記
Aが「第三者D」に相続分(相続分3分の1)を譲渡
BCD間で「Dの単有とする」旨遺産分割協議がまとまる。
BCからDへ「遺産分割」を原因とするBC持分全部移転登記を行う。
<数次相続が発生している状況で相続分の譲渡をする場合>
| 例: (1)被相続人A死亡(相続人(第1次相続人)は子 B・C・D) (2)子D死亡(数次相続人(第2次相続人) 子E) (3)第1次相続人の内の1人 BがCに相続分の譲渡 (4)第2次相続人のEがCに相続分の譲渡 この場合、被相続人A名義から直接、C名義に相続登記はできない。(平成4年3月18日民三1404号) |
<手続きの流れ>
「被相続人A」から相続を原因としてBCDに移転登記を行う。
D持分について「被相続人D」から相続を原因としてE名義にD持分移転登記を行う。
B持分について「相続分の売買もしくは贈与」を原因としてC名義にB持分全部移転登記を行う。
E持分について「相続分の売買もしくは贈与」を原因としてC名義にE持分全部移転登記を行う。
<異順位の共同相続人間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権移転の可否>
| 例:甲不動産の相続 (1)被相続人A死亡(相続人(第1次相続人)は子 B・C・D) (2)遺産分割協議未了のまま、子D死亡(数次相続人(第2次相続人) 子E・F) (3)第1次相続人の内の1人 BがEに相続分の譲渡 (4)第1次相続人の内の1人 CがFに相続分の譲渡 (5)EF間で遺産分割協議をしてEが単独で甲不動産を取得 この場合、相続分譲渡証明書及びEF間の遺産分割協議書を添付して「年月日(Aの死亡日)D相続、年月日(Dの死亡日)相続」を登記原因として、甲不動産についてAからEへの所有権移転登記の申請ができる。 <根拠> <上記の「平成4年3月18日民三1404号」の違い> 異順位の数次相続人間で相続分譲渡後、残りの相続人間で遺産分割協議が行われたかどうか (平成30年3月16日法務省民二第137号) |
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
最近、多くの方からお問い合わせいただいておりますが、ほとんどの方が「手続が分からないから依頼したいけど、どの位費用がかかってしまうのか」という点を大変気にされているようです。
そこで、当事務所では下記のお問合せについての相談料は初回無料です。
- 費用に関するお問合せ
- 手続に関するお問合せ
お気軽にお電話・お問合せフォーム・Eメールで御相談ください。
無料相談はこちら

当社へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
 求人情報を更新しました。
求人情報を更新しました。
こちらから⇒
お電話でのお問合せ
受付時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただければ
土日祝日、時間外の対応も可能
登記をオンライン申請
で行ないませんか?
当事務所では、登記も積極的に「オンライン申請」で行っております。現時点でオンライン申請を導入している事務所は、まだ少ないと思われます。
オンライン申請とは?

通常、登記申請書関係を各法務局へ直接提出するというのが原則的な方法でしたが、オンライン申請ですれば、申請書以外の必要書類は郵送でも可能であるため、交通費や日当などもかかりません。
アクセス

(旧横田・福村司法書士事務所)
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂
4丁目4番12号501号室
営業日
月曜日~金曜日
※土日、祝日も事前に御連絡があれば可能
営業時間
9:00~18:00
※事前に御連絡があれば時間外でも可能
業務エリア
さいたま市、蕨市、川口市他



